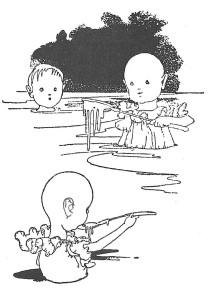『不思議の国のアリス』名言・名場面集
ルイス・キャロル (さとう@Babelkund訳)
第一章 兎穴に落ちる
兎穴はしばらくトンネルのようにまっすぐ続いていましたが、とつぜん下向きになって、それがあまりにとつぜんだったのでアリスは踏みとどまることなど考えるひまもなく、気がついたらとても深い井戸のようなところを落ちていました。
その井戸がとても深いのか、あるいはとてもゆっくり落ちているのか、どちらにせよ、アリスにはたっぷり時間があって、落ちながらまわりを見まわして、つぎにはなにが起こるのかしらと考えることができました。はじめ、下を見てどこに向かっているのか知ろうとしましたが、暗すぎてなにも見えませんでした。つぎに、井戸の壁に目を向けると、そこには食器棚や本棚がいっぱいあることに気づきました。ところどころに地図や絵がかけられているのが見えました。アリスは通りすぎるとき棚にあった壜を手にとりました。ラベルには「オレンジマーマレード」と書いてありましたが、残念なことに中はからっぽでした。アリスは壜を下に落としたくありませんでした。下にいるだれかを死なせてしまうかもしれませんからね。それで、通りすぎた食器棚になんとかして壜をおきました。
「そうだわ!」とアリスは心の中でつぶやきました。「こんなふうに落ちたあとなら、階段をころげ落ちたってへいちゃらだわ! 家の人はみんな、わたしのこと、とても勇気があると思ってくれるでしょう、きっと! そんなことで声をあげたりしないわ。たとえ家の屋根から落っこちたってね!」(それはほんとうに声を出すどころではないでしょう)
すぐにまたアリスは考え出しました。「地球をまっすぐ突き抜けてしまうんじゃないかしら! きっとおかしいでしょうね。頭を下にして歩いている人たちの中に出てしまったら! アンチパシリって言うんだっけ……」
「ダイナちゃん! わたしといっしょに落ちてきたらよかったのに! きっと空中にネズミはいないわね。でも、コウモリはつかまえられるかもしれなくてよ。コウモリはネズミにそっくりでしょ。でも、コネコはコウモリを好むかしら?」ここにきてアリスはちょっぴり眠たくなってきて、夢見るような口調で独り言を続けました。「コネコはコウモリをコノムかしら? コネコはコーモリをコノムかしら?」ときどきは「コネコをコーモリはコノムかしら?」
アリスが扉を開けると、その先には小さな通路が見えました。大きさはネズミ穴とあまり違いません。ひざまずいてのぞきこむと、通路の向こうには見たこともないような美しい庭がありました。その広間から抜け出して、きれいな花が咲きみだれる花壇とひんやりした噴水のあいだを歩き回ったら、どんなにすてきでしょう。でも、彼女はその戸口に頭を通すことすらできませんでした。「もし頭がどうにか通ったとしても」かわいそうなアリスは考えました。「肩が通らなければ、たいして役に立たないわ。ああ。望遠鏡みたいに体を折りたためればいいのにな! できると思うわ。最初にどうするのかさえ分かればね」だって、さっきからおかしなことばかり起きているので、アリスはほんとうに不可能なことなどほとんどないと思いはじめていたのでした。
でも、アリスはまずは数分間待ってみて、これ以上縮みそうにないか確かめました。このことについてはちょっぴりびくびくしていたのです。「だって、ほら」とアリスは自分に向かって言いました。「わたしがすっかり消えてなくなるかもしれないでしょ、ロウソクみたいに。そのときわたしはどんなふうになってしまうのかしら?」それからロウソクが吹き消されたあと、炎はどんなふうに見えるのか想像してみようと思いました。なぜって、思い出せる限りで、アリスはいままでそんなもの見たことがなかったのです。
第二章 涙の池
「ますますもってのほかのへんてこりん」とアリスは大声をあげました(とてもびっくりしたので、正しい言い方をころっと忘れてしまったのです)。「いまのわたしはいちばん大きい望遠鏡みたいに伸びているわ! さよなら、わたしの足さん!(アリスが足もとを見おろしたとき、どうやら足先はほとんど見えないところにあったようです。それほどどんどん遠ざかっていました)「ああ、かわいそうなわたしの足さん、これからはだれがあなたに靴やストッキングをはかせてくれるのかしら? ぜったいわたしにはできないもの! あなたの世話をするには、あまりにも遠く離れてしまっていることでしょう。できることは何とか自分でやってね。――でも足さんには優しくしなくては」とアリスは考えました。「さもないと、わたしの行きたい方向に歩いてくれないかもしれないし。そうね、クリスマスにはいつも新しいブーツをあげましょう」
それからアリスは心の中で、どうやったらいいか計画を練りました。「ブーツは配達の人に運んでもらうことになるでしょう」彼女は考えます。「そしたら、とってもおかしいでしょうね。自分の足に贈り物をするんですから! それに宛先もとても変なものになるわ!
炉格子隣り
暖炉前の敷物の上
アリスの右足様
(アリスの愛をこめて)
あら、なんてばかなこと喋ってるの!」
「ほんとに、もう! きょうはなんておかしな日なの! でも、きのうは何もかもいつもと同じ一日だった。夜のうちにわたしは変わってしまったのかしら? 思い出してみましょう。今朝起きたとき、わたしはわたしだったかしら? そういえば、ちょっと変だなと感じたのを覚えている。では、わたしでないなら、次の疑問は、わたしはいったいだれなの? ああ、それは難問だわ!」それからアリスは、自分と同い年だとわかっている子供たち全員に思いをめぐらせはじめ、その中に自分と入れ替わった子がいるか確認してみました。
「わたしがエイダでないことは確かだわ」とアリスは言いました。「あの子の髪はあんなに長い巻き毛になっているけど、わたしのはぜんぜん巻き毛になっていないもの。あと、わたしがメイベルっていうこともありえないわね。わたしはいろんなことを知っているもの。あの子のほうは、そうよ! あんなにもの知らずだもの! それに、あの子はあの子で、わたしはわたしだし。だから――やだわ、こんがらかっちゃう! 前に知っていたことをみんな覚えているか、確かめてみましょう。4・5十二、4・6十三、4・7――やだ! これじゃあ二十にたどりつけないじゃない! でも九九なんてどうでもいいわ。地理はどうかしら。ロンドンはパリの首都、パリはローマの首都、ローマは――だめだわ。ぜんぶ間違ってる、絶対! わたしはメイベルになっちゃったのよ! 『みごと小さな――』を暗唱してみるわ。
みごと小さなワニさんは
ぴかぴかしっぽをみがきあげ
ぎらぎらうろこのすみずみに
ナイルのしずくふりかける
なんと楽しげ 白い歯みせて
グワッとひろげた鉤爪と
ニカッとあいた大口で
お魚さんたち呼び寄せる
こんなのぜんぜん正しい歌詞じゃないわ」
アリスがそう言ったとき足がすべって、次の瞬間にはバシャン! あごまで塩水につかっていました。最初に思い浮かんだのは、どうかして海に落ちてしまったのだいうことです。「そういうことならば、汽車で帰ることができるわ」と独り言を言いました。(アリスは以前に一度だけ海水浴場に行ったことがありました。それで彼女が出した一般的結論というのが、どこでも英国の海岸に行くと、浅瀬にはたくさんの更衣車があって、砂浜では木のスコップで砂遊びしている子供たちがいて、ずらっと並んだロッジがあって、そうしたものの背後には汽車の駅があるということでした)
第四章 白兎、小さなビルを送りこむ
アリスが探し物をしていると、すぐに兎が彼女をみつけて、怒った調子で声をかけてきました。「こら、メアリー・アン、そこで何をしているんだ? いますぐ家にもどって、手袋と扇をもってくるんだ! さあ、急いで!」アリスはあまりにびっくりしたので、すぐさま兎が指さした方に走っていき、兎のまちがいを指摘しようとも思いませんでした。
(中略)
「なんてヘンテコなんでしょ」アリスは独り言を言いました。「兎の使い走りをさせられるなんて! つぎはダイナがわたしにお使いを言いつけることになるわね!」それからアリスは、こんなことが起きるかなと空想しはじめました。「『アリスお嬢さま! すぐにこちらへいらっしゃい。お散歩のしたくをなさい!』『すぐ行くわ、ばあや! でもダイナがもどってくるまで、このネズミ穴を見張って、ネズミが出てこないよう気をつけていなくてはいけないの』」アリスは続けます。「だけど、ダイナがそんなふうにみんなをこき使いはじめたら、家の中にはいさせてもらえなくなると思うわ!」
「おとぎ話を読んでいたときは、あんなことぜったい起らないと思っていたけど、いまここでまさにその真っ只中にわたしはいるんだわ! わたしについて書いた本があってもいいんじゃない! 大きくなったら自分で書いてやるわ――でも、もう大きくなってしまってる」アリスは悲しそうな声で付け加えました。「すくなくとも、ここではこれ以上大きくなる余地はないわね」
「ということは」アリスは考えました。「いまより年をとらないのかしら? それっていいかも――おばあさんにならなくてすむ方法だわ――ということは――いつまでも勉強するっていうことだわ! あら、そんなのいやよ!」
「あら、あなたはなんてお馬鹿さんなの、アリス!」彼女は自分に言い返しました。「ここでどうやって勉強するの? ほら、自分がいる余地だってほとんどないでしょ。教科書を置く余地なんてまったくないわよ!」
第六章 子豚と胡椒
それでアリスはその小さな生き物を下におろすと、ほっとして、その子が音も立てず小走りに森の中に去っていくのを見守りました。「あのまま育っていたら」とアリスはひとりつぶやきました。「ものすごく醜い子供になったとこだわ。でもあれなら、見た目のいいブタになれると思う」それからアリスは顔見知りの子供たちの中で、ブタとしてうまくやっていけそうな子たちのことに考えをめぐらせはじめ、ふと独り言をもらしました。「あの子たちを変える正しい方法さえ分かればね」
第七章 いかれたお茶の会
「むかしむかし、小さな三姉妹がいました」ヤマネが急いで話し始めました。「名前はエルシー、レイシー、ティリー。三人は井戸の底に住んでいました――」
「その子たちはなにを食べて生きていたの?」アリスがたずねました。食べることや飲むことになると、いつもとても興味をひかれるのです。
「糖蜜で生きていました」ヤマネはすこし考えてからそう答えました。
「そんなわけないわ」アリスがそっと言いました。「ぐあいが悪くなってしまうもの」
「その通り」とヤマネ。「とてもぐあいが悪かったのさ」
アリスは心の中で、そんな変わった暮らし方ってどんなだろうとちょっと想像してみましたが、頭がこんがらかるばかりでした。それで、こう続けました。「でも、その子たちはどうして井戸の底なんかに住んでいたの?」
「もっとお茶はどうかね」と三月兎がアリスに熱心にすすめました。
「まだなにも頂いていないわ」アリスはむっとした調子で答えました。「だからもっとなんてありえない」
「もっと少なくはありえないということかな」帽子屋が言いました。「ないものより多くするのは簡単だろ」
「あなたの意見など聞いてないわ」とアリス。
「今度は個人的なことをとやかく言っているのは誰かな?」帽子屋が勝ち誇ったように言い返しました。
アリスはそれに対する答えがどうしても見つかりませんでした。それでお茶とバター付きパンを自分でとって食べると、ヤマネのほうを向いて、質問を繰り返しました。「その子たちはどうして井戸の底なんかに住んでいたの?」
ヤマネはそれについてまた少し考えてから、言いました。「そこは糖蜜井戸だったのさ」
「そんなものないわ!」アリスは腹立たしそうに言い出しましたが、帽子屋と三月兎が「しっ! しっ!」と口をはさみ、ヤマネがむっとしてこう言いました。「おとなしくできないんだったら、きみが話のかたをつけたらどうだい」
「むりよ。どうぞ続けて!」とアリスがすまなそうに言いました。「もうじゃましないから。そういうのもあるかもね」
「そういうのがちゃんとあるんだ!」ヤマネが憤慨して言いました。
でも続けることを承諾しました。「そして、この小さな三人の姉妹たちはね――ドローイングの勉強をしていたのさ」
「なにをドローしてたの?」アリスがいまの約束をすっかり忘れて、ききました。
「糖蜜さ」今度はまったく考えこまずに、ヤマネは言いました。
「きれいなカップにしたい」と帽子屋が割って入りました。「みんな席を替えよう」
帽子屋はそう言いながら移動し、ヤマネがそのあとに続きました。三月兎はヤマネのいた席に動きまし。それでアリスはしかたなく三月兎の席に移りました。この席替えで得をしたのは帽子屋だけでした。アリスのほうは前よりずっと悪くなりました。三月兎がその席でミルク入れをひっくり返していたのです。
アリスはヤマネをまた怒らせたくなかったので、気をつけながら話しはじめました。「でも分からないんだけど、どこから糖蜜をドローしたの?」
「水は水の井戸からだろう」と帽子屋。「だから糖蜜は糖蜜井戸からに決まってる――そうだろ。頭が回らないのか?」
「でも井戸のなか深くにいたのよね」とアリスはヤマネに向かって言い、帽子屋に言われたことに気づかないふりをしました。
「そうだよ。その子たちは」とヤマネ。「深くて移動にはなかなか至らなかったが、いと仲良くて、そこにいるとなかなかぐあい良かったのさ」
この答えで、かわいそうにアリスは頭がこんがらがってしまいました。
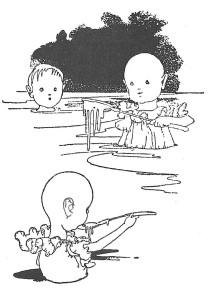
第九章 ニセ海亀の話
アリスは、公爵夫人がそんなに上機嫌だとわかってとてもうれしく思いました。そして、台所で会ったときあんなに怒りっぽかったのは、たぶん胡椒のせいにすぎなかったんだと、ひそかに考えました。
「わたしが公爵夫人ならば」と彼女はひとりつぶやきました(それほどなりたそうな口調ではありませんでしたが)。「台所に胡椒はぜったい置かないことにする。なくてもスープはおいしくできるわ――もしかしたら、人をかっかさせるのはいつも胡椒のせいではないのかしら」彼女は続けます。新しい法則を見つけたのでとてもうれしそうです。「それから、不機嫌で酸っぱい顔になるのはお酢のせい――それから苦虫をかんだような気分にするのはカモミールのせい――それから、それから――大麦糖とかの甘いものは子供の気持ちをスイートにしてくれる。みんながそのことを知ってくれたらいいのに。そうしたら、大麦糖をおしみなく使うでしょうにね……」
第十二章 アリスの証言
でも、アリスが去っていったとき、姉はじっとすわったままで、ほおづえをつき、夕日を見ながら、かわいいアリスのことや、話してくれたふしぎな冒険のことを考えていました。やがて姉もなんだか夢を見ているような心持ちになってきたのです。その夢というのはこうでした――
まず、彼女はかわいいアリスのことを夢に見ていました。さきほどのように、ちっちゃな両手が姉のひざの上でにぎりしめられ、きらきら輝く真剣なまなざしが姉を見上げてその目をのぞきこんでいました――妹の声の調子さえ耳にすることができましたし、すぐ目に入りそうになるほつれ毛をうしろにはらいのけようとして、おかしなふうに頭を上にそらせるさまを見ることもできました――さらには姉が耳をすますと、いえ耳をすますようにしていると、まわりじゅうが、かわいい妹の夢のなかのふしぎな生き物たちで活気づいてきました。
白ウサギがかたわらを急ぐとき、長い草が姉の足もとでカサカサ音を立てました――近くの水たまりをおびえたネズミがバチャバチャと泳いでいきました――三月ウサギとその仲間たちがいつまでも終わらないお茶の時間をすごすときの、カチャカチャいうティーカップの音も聞こえました。女王さまが運の悪い客人たちに死刑を宣告して退場を命じる金切り声も――もういちど、ブタっ子が公爵夫人のひざの上でくしゃみをしていました。そのまわりでは平皿や深皿がガチャンガチャンと割れています――もういちど、グリフォンの甲高い叫び声や、トカゲの持つ石筆が立てるキーキーいう音や、鎮圧されたモルモットたちの苦しそうな声。それらがあたり一面を満たし、あわれな海亀モドキが遠くですすり泣く声がそれに混じっています。
そうやって姉はすわって目をとじたままでいて、自分が「ふしぎの国」にいると信じかけていたのでした。でも姉にはわかっていました。もういちど目をあけさえすれば、すべてがつまらない現実に変わるということを――草は風に吹かれてカサカサ音を立てるだけでしょう。そして水たまりはアシのそよぎに向かってさざ波を立てるだけ――ティーカップのカチャカチャいう音はヒツジの首につけた鈴のチリンチリンいう音に変わるでしょう。そして、女王さまの金切り声はヒツジ飼いの少年の声に変わるのです――赤ん坊のくしゃみやグリフォンの甲高い声やもろもろのおかしな物音も、(姉にはわかっていたのですが)いそがしい農場からあがる騒がしい音の混じったものに変わるでしょう――また、遠くで牛たちがモーモー鳴く声は、海亀モドキがすすりなく太い声にとって代わることでしょう。
最後に姉は心に描きました。将来このかわいい妹が彼女自身おとなの女性になり、年を追ってどんどん成長していっても、ずっと子供時代の純真ですてきな心を持ち続けている様子を。そして自分のまわりに同じような小さな子供たちを集めて、たくさんのふしぎなお話や、もしかしたら、むかし見た「ふしぎの国」の夢のお話も聞かせて、みんなをきらきら輝く真剣なまなざしにさせている様子を。そして、子供たちの純真な悲しみをいっしょに感じ、純真な喜びをいっしょに味わいながら、自分の子どもの頃の生活やしあわせな夏の日々のことを思い出すことでしょう。