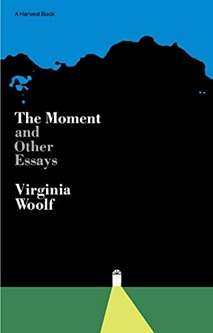【エッセイ】
ルイス・キャロル
ヴァージニア・ウルフ
さとう@Babelkund訳
しかしC・L・ドジソン師には形ある人生はありませんでした。彼はあまりにも軽々と世の中を通り抜けたので、書かれたものは残されていません。彼はオックスフォードのなかに逆らわずに溶け込んでいたので、目につきませんでした。あらゆる慣習を受け入れました。とりすまし、気むずかしく、信心深く、そして滑稽でした。十九世紀のオックスフォードの学者の真髄があるとすれば、彼こそその真髄でした。彼は善良そのものだったので姉妹に崇められ、純粋そのものだったので甥になにもいわれませんでした。甥がほのめかしているように、「失望の影がルイス・キャロルの人生を覆っていた」という可能性はあります。ドジソン氏は即座にこの影を否定しました。「わたしの人生にはいかなる裁判や災難も縁がなかった」と彼は言っています。ですが、この無彩のゼリーのなかにきわめて硬質な結晶が埋まっていました。子どもらしさを含んでいたのです。そしてこれはとても奇妙なことでした。なぜなら子どもらしさは通常、しだいに消えていきます。その少年あるいは少女が大人の男や女になったとき、子どもらしさの断片は生き残っています。子どもらしさは昼間にときどき戻ってきます。夜にはもっと頻繁に戻ってきます。しかしルイス・キャロルの場合はそうではありませんでした。どうしてかは分かりませんが何らかの理由で、彼の子どもらしさはくっきりと分かれていました。それは彼のなかに完璧なまま宿っていたのです。それを追い払うことはできませんでした。そして、それゆえに年を重ねるうちに、彼の存在の中心にあるこの邪魔もの、この純粋な子どもらしさというしっかりした固まりは、成人男子から養分を奪っていったのです。彼は大人の世界を影のように擦り抜けていきました。確固たる姿になるのは、唯一、イーストボーンの波打ちぎわで小さな少女たちといっしょにいて、スカートの裾を安全ピンで留めてあげるときだけでした。しかし子どもらしさが彼のなかにそっくり残っていたがために、彼はほかのだれも為し得なかったことをすることができたのです――彼はあの世界に戻ることができたのです。その世界を再現することができ、それでわたしたちも再び子どもになれるのです。
わたしたちを子どもにするために、彼はまずわたしたちを眠らせます。「下へ、下へ、下へ、この落下に終わりはないのかしら?」下へ、下へ、下へとわたしたちが落ちていく先は、恐ろしく、ひどく支離滅裂で、それでも完璧に論理的な世界なのです。そこでは時間は目まぐるしく進み、つぎにはぴたりと止まります。そこでは空間は伸びて、つぎには縮みます。それは眠りの世界です。それは夢の世界でもあります。なんら意識的な努力をしなくても夢は訪れます。白ウサギ、セイウチ、大工と、つぎつぎ入れ代わり、飛び跳ねながら頭のなかに浮かんできます。二冊のアリスが子どもたちの本でないのは、そういうわけなのです。わたしたちが子どもになることのできる唯一の本なのです。ウィルソン大統領、ヴィクトリア女王、タイムズ紙の論説委員であった後のソールズベリー卿――あなたが何歳であろうと、重要人物であろうと、あるいは名もない者であろうと、かまいません。もういちど子どもになれます。子どもになるということは、まさに文字通りの意味です。なにもかもがとても不思議だと気づくので、驚くことは何もありません。薄情であり、無慈悲であり、それでも冷たいあしらいや蔭りがその世界を薄闇でおおうほどに情熱的なのです。それが不思議の国のアリスになるということです。
それは鏡の国のアリスになることでもあるのです。それは世界を上下さかさまに見ることです。これまで幾多の偉大な風刺家や道徳家たちがわたしたちに世界をさかさまに見せました。大人がそれを見るように、痛烈な様子で見せたのです。ルイス・キャロルだけが子どもが見るような目で、わたしたちに世界をさかさまに見せてくれたのです。そして、子どもたちが笑うようにわたしたちを無心に笑わせてくれました。純粋なナンセンスの木立を抜けて歩き回りながら、わたしたちは笑います、ひたすらに――
一同は シンブルと心配を抱いて探し求め
フォークとホープをもって追い求めたのだ……
(訳注:『スナーク狩り』の一節)
それからわたしたちは目を覚まします。不思議の国のアリスのなかの変化はどれもそれほどおかしなことではありません。なぜなら、わたしたちは目覚めて気づくのです――これはC・L・ドジソン師なのか? ルイス・キャロルなのか? それとも両方が結合したものなのか? この複合体は、英国の少女たち向けにシェイクスピアの超短縮版を作ることをもくろみ、彼女たちが観劇に行くときに、死について考えることを切に求め、そしていつもいつも、「人生の真の目標は人格形成で……」と気づいてくれることを求めるのです。それでは、一二九三ページのなかにも「完全性」というものはあるのでしょうか?(一九三九年一月執筆)
【解説】
このエッセイが収載されているThe Moment and Other Essaysはヴァージニア・ウルフ(一八八二〜一九四一)の死後、夫のレナード・ウルフが編纂したもので、一九四七年に発刊されています。このエッセイの一部がジャッキー・ヴォルシュレガー著『不思議の国をつくる』(河出書房新社)の「ルイス・キャロル」の章で引用されています(五一〜五二ページ)。